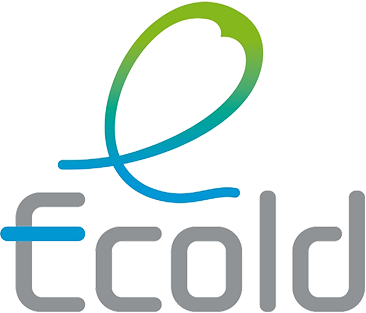ダウン症の子どもと発育~社会性~
こんにちは。ガイドヘルパーとして働いております、るりと申します。
ダウン症で重度知的障害を持つ弟がいる、姉でもあります。
前回の記事では、ダウン症児の学習に焦点を当てました。
本記事では、ダウン症児の社会性、人間関係の構築に関する部分をご紹介します。
*本記事では、障害を社会モデルで捉え、社会側にある障害に自覚的になり、改善するように働きかけたいという願いを込めて、あえて「障害」と表記します。
ダウン症児の社会性の発達の特徴
これまでにご紹介してきた特徴と重なる部分もありますが、改めてダウン症児の社会性に関わる特徴をご紹介いたします。
まず、一般的に言われるのはダウン症の子どもは「人懐っこい」と表現されるように、人と関わるのが好きな子が多いです。
もちろん、個々の性格による部分はありますが、私の弟も小さいころから、町ゆく人々に自分から挨拶をしたり、話しかけられると笑顔で応えたりしていました。
ただし、乳幼児期は反対に、反応が薄いと感じる保護者様も多いようです。
ゆっくりではありますが、徐々にコミュニケーションが取れるようになるにつれ、感情が豊かに表現されるようになります。
また、感情が育つと、喜怒哀楽がはっきり表情や行動にでやすいとも言われています。
ここは、周囲の人にポジティブに受け入れられ、人から好かれる部分でもあります。
一方、年齢が上がるにつれて、特に負の感情のコントロールの面では他のお子さまとの差が出てきやすくなるかもしれません。
社会性の発達の遅れによって、思春期以降に社会的なつながりが希薄になってしまう場合もあるようです。
この結果、運動する機会が減ってしまうことや、不規則な生活習慣によって、肥満に繋がる部分もあるようです。
心身の健康のためにも、幼少期から社会性を身に付けていくことは大切だと考えられます。
家族や周囲ができるサポート
人間関係を構築する上で、まず基礎的な生活能力があることが、身だしなみや清潔感、心情面に影響を与えるため重要です。
これは小さなお子様を持つ方であれば、みなさん気を配っているところかと思います。
ダウン症児の発達は、どうしても他の子どもに比べるとゆっくりとしています。
根気強く向き合いつつ、支援が必要な部分と、自律させていく部分を見極めていくことで、成長につなげることができます。
具体的なトイレや歯磨きのトレーニングについては、コラム内の別の記事でもご紹介しておりますので、ぜひご参照ください。
この自律が進むことで、お子さま自身が支援を受けやすい状態になることができます。
生活習慣は幼少期からの積み重ねが重要です。
ぜひご家庭でも規則正しい生活を意識してみてください。
さらに、コミュニケーションの最初の一歩となる「挨拶」をご家庭でも練習していくと、幼稚園・保育園や支援サービス内でもコミュニケーションのきっかけとなっていきます。
「ありがとう」「ごめんね」「おはよう」「いただきます」
など、毎日使う挨拶は、なるべく一緒に言う練習をしていくと良いかもしれません。
加えて、ロールプレイを取り入れた、いわゆる「ごっこ遊び」を通して、感情面や人間関係の構築のスキルアップにも繋がっていくようです。
このように、ご家族の間だけでなく、集団の中での振る舞い方を実践しながら学ぶことも、成長に繋がります。
弊社では、集団遊びを取り入れながら社会性の発達を促します。
また、「おやつ」の場面一つをとっても、「選ぶ」という主体性を重んじています。
自発的に「選ぶ」ことでコミュニケーションのきっかけにもなります。
小学校入学前の早期段階で集団で過ごすことが、お子さまのさらなる成長の刺激になるはずです。
少し余談にはなりますが、ダウン症児の保護者様にとっても、同じように障害児を持つ保護者さんとのネットワークに所属することは大切なようです。
幅広い年代の児童の親のネットワークがあることで、ダウン症児の将来についての情報収集ができ、親の不安が軽減されることもわかっています。
まとめ
以上のように、ダウン症児の社会性の発達は、定型発達に比べるとゆっくりとしたペースではありますが、持ち前の人懐っこさや豊かな感情が活躍する場面でもあります。
弊社でも、社会性の発達に力を入れたプログラムを実施しております。
また、様々な年代のお子さまにご利用いただいているため、より豊かな人間関係を構築する学びの場にもなると考えております。
幼少期に社会性を発達させることで、成人後も周囲との関係を上手く調整できることで、仕事にも活かされるスキルとなっていきます。
なにより、友人ができることはお子さまの人生に彩りを与えることは間違いありません。
弊社では、専門職、スタッフへのご相談も随時承っておりますので、お気軽にお声掛けください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【参考文献】
● 山内通恵, 吉永砂織,鶴田来美,「青年前期にあるダウン症児の社会参加に対する親の思いと取り組み」,2022,南九州看護研究誌20(1),,1-9
● 伊麗斯克,菅野敦,「ダウン症児・者の「対人関係」に関する文献研究 ── 研究動向と先行研究の分析を踏まえて ──」,2012,東京学芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ63,263 – 275
前の記事へ