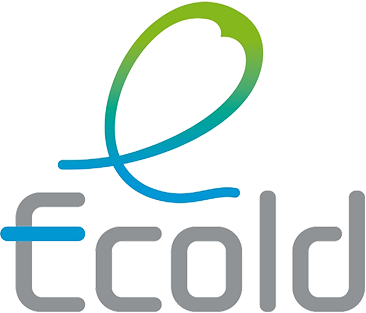ダウン症の子どもと発育~学習~
こんにちは。ガイドヘルパーとして働いております、るりと申します。
ダウン症で重度知的障害を持つ弟がいる、姉でもあります。
前回の記事までは、コミュニケーション発達支援として有効な手段である、PECSについて扱いました。
本記事では、ダウン症児の、いわゆる学力とされる部分の学習について注目します。
*本記事では、障害を社会モデルで捉え、社会側にある障害に自覚的になり、改善するように働きかけたいという願いを込めて、あえて「障害」と表記します。
目次
書きやすい、覚えやすい教材の工夫
これまでの記事でもご紹介してきた通り、ダウン症児には先天性の特徴があります。
それゆえに、小学校入学時に、知的発達としては早すぎるタイミングで学習がスタートしてしまうということが起こりえます。
その前段階である未就学時、または入学後からでもできる学習をスムーズに進めるポイントとして、まずは教材の工夫をご紹介します。
これまでの記事と重複しますが、ダウン症児は健常児に比べると細かい動作を苦手とする場合が多いです。
そこで、以下のような工夫があると学習しやすくなります。
● 点つなぎ・なぞり書きで手の動きを練習する
また、視覚情報の方が得意な子が多いため、以下のようなポイントで教材を選ぶのがおすすめです。
● 大きな文字、色がはっきりしているもの
● 好きなキャラクター/ものが描かれているもの
以上の観点は、ダウン症児以外でも、幼児期の学習に大切なポイントとなります。
お子様の発達段階に合わせて、小学校入学後でも取り入れてみると、学習しやすくなるかもしれません。
数の概念を理解するための工夫
視覚優位という特性を持つダウン症児にとって、抽象的な概念を理解するのは難しい場合があります。
特に、小学校入学直後に学ぶ、足し算・引き算や時計の読み取りでつまずく可能性があります。
そのため、以下のような工夫がおすすめです。
● 生活の中でも時計を使う(「長い針が12になったら3時だからおやつだね」の声掛けなど)
● 絵本の読み聞かせを通じて学ぶ(音の出るものだとより効果的)
● 買い物ごっこなど遊びで計算をしてみる
以上のように、目に見える形で学習しつつ、生活や遊びの中に取り入れて関心を持たせることが大切です。
アプリの活用
学び始めて気になってくるのが、定着のスピードかもしれません。
ダウン症児は短期記憶の保持が苦手な場合があるため、繰り返し学習が健常児以上に必要な場合があります。
根気強くお子様に付き合うのも良いですが、最近では繰り返し学習を手軽にできるアプリもたくさん提供されています。
特に、音や視覚に刺激があるアプリでの学習が合っている子もいるようです。
また、アプリだけではなくYouTubeなどでも学習向けの動画も出てきています。
このように、上手くデジタル教材を活用するのも一つの手になりそうです。
まとめ
ダウン症児に関わらずですが、お子様はできることが一つ増えるたびに、どんどん自信をつけていきます。
自信がつくと、意欲的になり、次の学習のモチベーションへと繋がっていきます。
もしかすると、親としてお子様に一番すぐにできることは、「褒める」ことかもしれませんね。
弊社でも、ひとりひとりのお子様に寄り添った支援を行っており、モチベーションになるような声掛けも心がけております。
何かお困りの際は、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【参考文献】
● 真鍋健 ,東原文子,「ダウン症児に対する就学直後の平仮名入門期指導の一事例 ─間違った書字パターンが定着していた特別支援学級在籍児童への介入を中心に―」,2021,千葉大学教育学部研究紀要(69),217-222
● 古山千佳佳,落合俊郎,「特別支援学校における教員と作業療法士の協働ー色塗りが上手になった事例を通してー」,2015,特殊教育学研究59(3),205-213
次の記事へ