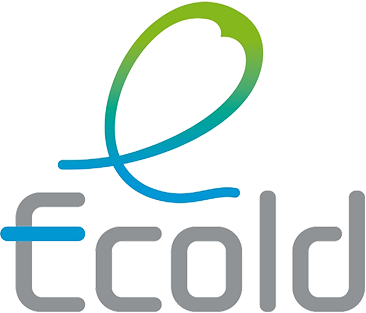「癇癪との向き合い方」シリーズ 第2回:何時間も泣き続ける子の癇癪が収まった?!~切り替える力と他の児童との関係づくりからの学び~
こんにちは。ガイドヘルパーとして働いております、るりと申します。
ダウン症で重度知的障害を持つ弟がいる、姉でもあります。
今回から4つの記事で、癇癪(かんしゃく)について、弊社の代表である野口にインタビューを行った様子を連載します。
第2回となる本記事では、第1回でもご紹介したお子さまの癇癪に、教室が具体的にどう向き合ったのかをお伝えします。
専門機関である療育とはいえ、癇癪へのアプローチは一筋縄ではいきません!
それでも奮闘する様子を赤裸々にお話しいたします…!
*ご紹介するケースは保護者様に許可をいただき掲載しております。
*本記事では、障害を社会モデルで捉え、社会側にある障害に自覚的になり、改善するように働きかけたいという願いを込めて、あえて「障害」と表記します。
目次
1. 現場での試行錯誤「やりたいことをやらせてみる」
野口:その子は、癇癪を起こすともう何時間でも、ほんとに2時間とか泣き続けるんですね。
一回、好きにやらせたんですよ、もう何やってもいいと。
結構いろんなものを投げたりとかですね、もう1時間ぐらいずっとやってましたよ。
いすを投げたり、床材を剥がしたりと色々やってましたね。
それで普通は収まると思ってました。
でも全然収まらない。
私が心理を大学院で勉強していた時に、自分の怒りやイライラが発生してから何分継続するのかを日記につける課題をしていたことがあって、その時知ったことが、怒りやイライラに支配されても、そんなに長い時間続かないということでした。例えば混んでいる電車内で足を踏まれてイライラしても次の駅を過ぎるころには忘れているとか。
だから、やりたいことやらせてみたら、収まるのかなと思って見ていたら、すごい持続力がありました。
るり:いや~そうですよね。
ずっと怒っているのも体力がいりますよねぇ…。
野口:そうなんですよ。
ただ、今でも唯一癇癪を起こす状態になるのが、寝起き。
送迎してる時に車の中で寝ちゃうんですよね。
本来であれば自分の足で歩いて帰ってほしいっていうのがあるので、私以外のスタッフもそれをトライしたことがあるんですけど、いずれもダメで。
うわーってなって、「だっこだっこ!」で、もう歩かない。
もう寝起きは非常に悪いですね(笑)
で、もう起こすのやめようと。
これ、育てとして望ましいことをやろうとしましたが、この子にとっては意味がないと思って、もう担いで、ママにそのままお渡しすることにしました。
るり:じゃ、寝てる状態で?
野口:寝たまま起こさないで、半分寝ぼけたような感じではあるんですけど。
担ぐと、その児はたぶんわかってるんですけど(笑)
でもそれは本人の希望が叶っているので、わざと起きないっていうのもたぶんあるなって。
るり:子どもっぽいですね、そこは。可愛いらしい(笑)
野口:うんうん。
でも、寝起き以外はほんとにもう一切、(癇癪に)ならないですね。
2. 最初は「泣かせる」→今は「切り替えを促す」への転換
るり:では、これほど激しく癇癪をおこしていた子が、おこさなくなる。
それはどうしてなんでしょう?
野口:教室のスタッフは、上手く切り替える技をいろいろ編み出しててですね。
その子の好きなものをスマホだったり、人形だったりを持ち歩いて見せたりして、切り替えさせたり。
「バス走ってるよ」とかって気をそらせて、泣き止ませたりとかですね。
それでも泣きやまなかったら、「じゃあ散歩行こう」って収めたりとかですね。
いろんな技を駆使して、だんだん泣かなくなってきたっていうのはありますかね。
好きなだけ泣かせようは全く何の効果もなくて(笑)
やっぱり切り替えさせることなんですよね。
収める方法が何かっていうことを色々編み出して、だんだん泣かなくなってきて。
だんだんコミュニケーションを取れるようになってきて。
お家ではどうかわからなかったですけど、事業所ではあんまりわがままとか言わなくなっていて、癇癪が起きなくなっていったという感じでした。
1年ぐらい経ったら、保護者さんの面談の時に「癇癪がなくなりまして」って言われまして。
ものすごい感謝いただいて、びっくりしちゃって、こっちが(笑)
るり:それは、すごい進化ですね!
野口:はい(笑)やっぱり親御さんとしてはお外で全力で泣かれるのが恐怖だったようです。
るり:自分で切り替えられる技を見つけていけるようになってくると、寝起きとかもうまくなっていくのかもしれないですね。
野口:うん、寝起きは課題として残ってるかもしれないんですけど、これから成長していくんだと思います。
3. 他の児童との関わりからの学び
るり:いろいろと切り替える技を試して、癇癪をおこさなくなっていたというお話でしたが、他にも癇癪がなくなる要因はあったんでしょうか?
野口:はい。3歳の時から来て、4歳では今のようになっています。
その時に、親御さんから報告をいただいたのは、その児の下にお子さんが生まれて、下の児の面倒などかなり見てくれるらしくって。
るり:なるほど。そこももしかしたら、きっかけとしてあったのかもしれないですね。
野口:そうですね。
教室も自分と同い年とか、自分より下の児がいるので、そういう児の面倒見も結構いい方で。
スタッフが何も言ってないのにやってあげちゃうみたいな、そういう傾向はあって。
そのせいかは、わからないですけど、なんか満たされて、癇癪を忘れちゃっているみたいです。
るり:忘れちゃう。
野口:忘れちゃったっていうぐらい、何も起きないんですよ。
前は「あ、(癇癪が)来る来る来る来る」っていう感じあったんですけど、今は全然ないですね。
「これやっちゃダメだよ」とかって言ったら、前だったら癇癪になったかもしれないのに、もう全くない。
「わかった」みたいな。
やっぱり、本人なりに色んなコミュニケーションを獲得したんじゃないのかなとは思います。
るり:どういう方法でコミュニケーションできるようになったんですかね?
野口:教室でみてる限りではありますけど、同じぐらいの年代の子と遊んでいるうちに、いろんなコミュニケーションを覚えた感じがしますね。
るり:なるほど。ほんと、遊んでるうちに成長したんでしょうね。
普通の発達段階における成長を迎えたんでしょうね。
野口:うん、そうかもしれないです。
治ったとかじゃなくて。
るり:今までこうできなかったことができるようになったことで、満たされたというか、表現できるようになったものがあったのかもしれないですね。(第3回へ続く)
まとめ
第2回では、一度やりたいことを好きにしてみてもらう試みをしてみたものの、惨敗した様子をお話ししました。
長時間もの間泣き続ける癇癪をもっていたお子さまも、切り替えを身に付けながら、他のお子さまとのかかわりの中で、コミュニケーションを獲得された様子。
第3回では、そんなお子さまの成長過程に注目して、さらに語りを深めてまいります!
ぜひ、次回もお楽しみに!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
エコルド川口教室です

埼玉県川口市で児童発達支援・放課後等デイサービス多機能型事業所を運営しております。
未就学および小学生低学年の課題のあるお子さまに「療育×テクノロジー」をテーマに療育をご提供しています。
エコルドグループの特色である未就学のお子さまを平日17:30までお預かりしていることで保護者さまから喜ばれております。
お問い合わせ、ご見学申し込み、ご相談だけでもお気軽にどうぞ