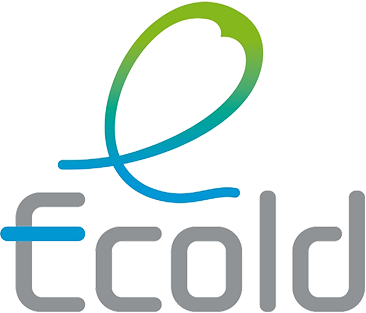「癇癪との向き合い方」シリーズ 第1回:癇癪は「伝える手段」の1つ~お子さまの気持ちに寄り添う第一歩~
こんにちは。ガイドヘルパーとして働いております、るりと申します。
ダウン症で重度知的障害を持つ弟がいる、姉でもあります。
今回から4回に渡って、癇癪(かんしゃく)について、代表の野口にインタビューを行った様子を連載します。
第1回となる本記事では、運営する療育施設で出会ったとあるお子さまとの経験と、そこから癇癪について学んだことをご紹介いたします。
癇癪でお悩みの保護者様と近い立場で考え、向き合っていく様子をお伝えします!
*ご紹介するケースは保護者様に許可をいただき掲載しております。
*本記事では、障害を社会モデルで捉え、社会側にある障害に自覚的になり、改善するように働きかけたいという願いを込めて、あえて「障害」と表記します。
目次
1. 「癇癪=わがままではなく、伝えるための手段」という考え
るり:癇癪についてというざっくりとしたテーマで始めたいと思います。
記事も2本書かせていただいたところで、野口さんが思う癇癪ってなんだろう?というところを、ざっくばらんにお話していただければと思います。
野口:ありがとうございます。
究極の解決は、2本目の記事に書いてあった通りだと私も思っています。
要は、コミュニケーションができないので、伝える手段として、泣きわめくなどの癇癪になっているんじゃないのかな?ということですね。
つまり、癇癪で自分の我を通したいっていうのは1つあります。
けれども、お子さまが癇癪という対処を覚えてしまうと、それをなくすのはなかなか難しいかもしれない。
だからこそ、自分の意思がうまく伝わらないということで癇癪になっているのであれば、早期段階でコミュニケーションを身につけることによって、なくなっていくんだろうなっていうのは、実感としてあります。
るり:そうですね、おっしゃる通りだと思います。
野口:はい。でも、自分の我を通そうと思って泣きわめくっていう手段になってしまう子は、本人にはどうしようもないと思ってるんですね。
るり:どうしようもないというのは?
野口:どうしようもないというか、「泣いたって(全部は)叶わないんだよ」って伝えることを、もう時間かけて向き合っていくしかないのかなって思っていて。
るり:なるほど。癇癪によって、なんでも言うことを聞いてもらえるわけではないということを丁寧に伝えていくんですね。
2. コミュニケーションの発達と癇癪の関係についての考察
るり:そういえば、癇癪の記事を作成する際に、実際にエコルドのご利用者さんにニーズがあると伺いましたが、どのようなケースだったんでしょうか?
野口:はい、エコルドに入った時は年少さんで、今年、年長さんの子が、もうとにかく癇癪がひどいとお母様からご相談を受けまして。
見学の前には、癇癪のことを深くは聞いておらず、実際にお子さまが来てみると、すぐに、「あれ?」っていう感じで。
すごく泣くっていうことを、継続できる子だったんですよね。
すごくっていうのは、1時間じゃ収まんないんです。
るり:ええ!すごい元気ですね(笑)
野口:はい(笑)
でも、結論、現在そのお子さまの状態をお伝えしておくと、全く癇癪にならないんですよ。
るり:素晴らしい。なぜでしょうね?
野口:それはなんでかというと、たぶん、コミュニケーションが発達したからだと。
るり:へえ、やっぱりそこなんですね~。
具体的にはどのような癇癪だったんですか?
3. 実際のケース紹介と親御さんの困りごと ― 何時間でも泣き続ける
野口:そのお子さまの、ご利用時の最初のエピソードとしては、みんなで散歩に行きましょうって散歩するっていう時に、もうくたびれたと。
「だっこ」って言って、「いや、だっこしないよ」って言ったら、泣き出したんですよね。
それも、地面に寝転がって。
もう全く地面から動かない(笑)
それで、ずっと泣かせてみたんです。
他のお友達、スタッフとかも先に行かせて、私が残って。
それも1時間ぐらい泣いてたかもしれないです。
でも、「だっこしないよ」って、結局だっこしないで、どれぐらい(癇癪が収まるのに)かかるのかなと思って。
それで、こんなに泣くんだと思って、ママさんに聞いたら「そうなんですよ」と言われて。
不満があるんだったらね、不満を思いっきり感じて、泣くだけ泣いたらいいんじゃないのっていうのが私の考え方だったんですけど。
さすがに長時間ずっと泣き止まないのは大変だなと。
だから、例えば興奮したら別室に入ってもらって、気分切り替えましょうとしてみたりというか。
そういう技があるじゃないですか。
それは全く効かなくて(笑)
場面が変わろうと、なんだろうと泣き続けるんですよ。
それで、親御さんに、「普段こんな感じですか?」と伺ったら、
「そう、そうなんです。家でもそうなんです。」と。
「街中で1回癇癪が始まっちゃうと、ずっと泣いていて。
それで叱ったりなんかしちゃったりすると、ずっと続くんです。
でも、あまりにも続くので、通行人の人から通報されたことがあります」
とおっしゃるんですね。
るり:癇癪やパニックの時にありますよね。私もガイド(ガイドヘルパー、移動支援)中に怪訝な顔で見られたりします。
野口:そうですよね。
お母様としては、「どうしたらいいかわかんなくって」っていうのが、このデイを使った理由だったんですね。
<第2回へ続く>
まとめ
第1回では、これまでの記事でもご紹介した内容とも重複しますが、「癇癪=伝える手段」として起こっている、という考えをお話してきました。
そのため、癇癪を収めるには、「コミュニケーションの発達」が鍵になってきます。
第2回では、このお子様と弊社の向き合い方と、どうにかして気持ちを切り替える技を見つけるべく、試行錯誤した様子を記します。
ぜひ、次回もお楽しみに!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
エコルド川口教室です

埼玉県川口市で児童発達支援・放課後等デイサービス多機能型事業所を運営しております。
未就学および小学生低学年の課題のあるお子さまに「療育×テクノロジー」をテーマに療育をご提供しています。
エコルドグループの特色である未就学のお子さまを平日17:30までお預かりしていることで保護者さまから喜ばれております。
お問い合わせ、ご見学申し込み、ご相談だけでもお気軽にどうぞ