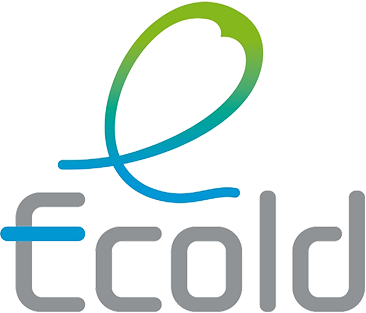癇癪(かんしゃく)の原因と対処法
こんにちは。ガイドヘルパーとして働いております、るりと申します。
ダウン症で重度知的障害を持つ弟がいる、姉でもあります。
今回のテーマは、「癇癪(かんしゃく)」です。
(以下、「癇癪」と表記します。)
どんなにかわいい我が子でも、いきなり泣き叫んだり、暴力的になったりすると、辛いですよね。
「なんで急にスイッチが入っちゃったんだろう?」
「どうしたら収まるんだろう」
「お友達にけがをさせたらどうしよう」
そんな不安をお持ちの保護者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本記事では、癇癪の原因と対処法をご紹介いたします。
*本記事では、障害を社会モデルで捉え、社会側にある障害に自覚的になり、改善するように働きかけたいという願いを込めて、あえて「障害」と表記します。
目次
癇癪ってなに?
癇癪(かんしゃく)は、様々な特性を持つ子どもによく見られる行動の一つです。
発達障害、自閉症、知的障害、ダウン症、強度行動障害など、障害の種類は問わず、現れる可能性があります。
具体的には以下のような行動を指します。
● 大声で泣く
● 突然叫ぶ
● 床に寝転がる物を投げる
● 他者を叩く

これらの行動は、周囲の人だけでなく、お子さま自身にとってもストレスになることが多いです。
癇癪は「わがまま」ではなく、「自分の気持ちを言葉でうまく伝えられない」という「感情の爆発」です。
では、どのような「気持ち」が癇癪の裏には隠されているのでしょうか?
その「気持ち」と対処法を次にご紹介いたします。
原因と対処法
癇癪が起こる背景には様々な感情と、それを生み出す要因があるとされています。
この要因にあった対応をすることで、癇癪が収まってくることもあります。
そこで、4つの大きな要因とその対処法についてご紹介いたします。
① 見通しが持てないことによる不安
「今から何が起こるのか」「次に何をするのか」といった見通しが特性によってわからない場合があります。
そのため、突然の変更による混乱や不安が上手く言葉にできないことで、癇癪のきっかけになりやすいです。
〈対処法〉
● スケジュールを絵カードやタイムタイマーなどで視覚的に伝える
● 「あと3分で帰るよ」など具体的な時間を示し、事前に予告する
● 急な変更がある場合は、視覚的に説明をし、代替案を出してみる
このように視覚的なサポート、例えばアナログ時計を用いて説明すると、理解しやすい場合があります。
また、何か変更がある場合は、次はいつできるのかや、今から何をするのかを明確にすると安心に繋がります。
② 感覚過敏や感覚鈍麻
聴覚・視覚・触覚などの刺激に過敏な特性を持っていることもあります。
逆に鈍感な子もいます。
そんな子どもの場合は、特定の音や光、匂い、服の肌ざわりなどが不快で、癇癪につながることがあります。
〈対処法〉
● イヤーマフやサングラスなどで刺激を軽減する
● 着るものや食べ物など、本人が好きなものを選ばせる
● 苦手な場面(人込みやうるさい場所)は避けたり、事前に伝える
このように、好きな感覚のものに囲まれて過ごすことが心の安定につながります。
また、苦手な場面も事前に説明し、経験を積み重ねることで慣れてくる場合もあります。
ただし、特性を無理に克服させることは、かえって強いストレスになる場合もあるため、専門家との相談をお勧めします。
③ 言葉での表現が難しい
言葉で思いが伝えられなくて、行動に現れる、というのも一つの原因です。
特に、知的障害やダウン症、強度行動障害、ASDの子どもにはこうした場面が多く見られます。
〈対処法〉
● 絵カードや指差し、ジェスチャー、簡単なキーワードなどの、言葉以外でできそうな伝え方を教える
● 選択肢を提示する 例:「ジュースと水、どっちがいい?」
● 癇癪が収まったあとに、「○○が嫌だった?」と言葉にすることで、次回から言葉にしやすくなる
④ 切り替えが難しい・予定が変わることへのこだわり
自閉症やダウン症の子どもには、同じ行動を繰り返す安心感があります。
好きなことを途中でやめないといけないストレスが、癇癪のきっかけになっている可能性もあります。
〈対処法〉
● 時間の見える化(タイマー・時計・秒数カウント)をする
● 「あと1回だけね」「これが終わったらおしまい」など、丁寧に終わりのタイミングを伝える
● 「終わったらシールを貼ろうね」など、代替行動を用意することで納得しやすくなる
以上のように、お子さまの見えない気持ちを言語化してあげたり、その不快感の原因に対処することで、癇癪との付き合い方が見えてくる可能性があります。
まとめ
癇癪の対応には、日々の安心できる関係性が大切です。
お子さまは、癇癪中に「誰かが見てくれている」「受け止めてくれている」と感じ、安心することで、次の対処する段階へと動きやすくなります。
保護者様も、怒りたくなる気持ちを抱えながらも、根気強く向き合うことで、ご自身の気持ちとお子様を見守る気持ちのバランスを整えていくことができるようになっていきます。
この根気強く向き合う中で、保護者様だけでなく、周りの支援者を頼ることも重要になります。
次の記事では、園や支援先で、お子さまの癇癪をどう伝えて、どのように連携していくことができるかをご提案します。
ぜひご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
当教室でも、お子さまの特性や、癇癪についても相談を随時承っております。
気になることがございましたら、お気軽にお申し付けください。
【参考文献】
● 川村立,「無発語自閉スペクトラム症児1例のCOVID-19環境下での 他職種連携を通じた支援 〜自己刺激行動を代替行動分化強化へ高次化した取り組み〜」,2025,リハビリテーションと応用行動分析学11(0),5-9
● 當眞正太,城間園子,「強度行動障害のある児童の伝える力を高めることを目指して -環境の調整と関係性の形成を中心とした関わりから-」,2024,高度教職実践専攻)教職大学院)紀要8,89-100
エコルド川口教室です

埼玉県川口市で児童発達支援・放課後等デイサービス多機能型事業所を運営しております。
未就学および小学生低学年の課題のあるお子さまに「療育×テクノロジー」をテーマに療育をご提供しています。
エコルドグループの特色である未就学のお子さまを平日17:30までお預かりしていることで保護者さまから喜ばれております。
お問い合わせ、ご見学申し込み、ご相談だけでもお気軽にどうぞ
次の記事へ