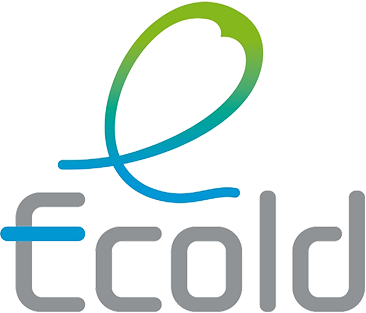ダウン症の子どもときょうだい児 ~きょうだい児へのサポート~
こんにちは。ガイドヘルパーとして働いております、るりと申します。
ダウン症で重度知的障害を持つ弟がいる、姉でもあります。
これまでの記事では、ダウン症児の発達に関して、様々な観点から見ていきました。
本記事では、ダウン症児の兄弟にも注目して、どんなサポートができるかを考えていきます。
*本記事では、障害を社会モデルで捉え、社会側にある障害に自覚的になり、改善するように働きかけたいという願いを込めて、あえて「障害」と表記します。
目次
ダウン症児のきょうだい児の気持ち
以前の記事でもきょうだい児の気持ちについてはご紹介してきました。
その内容を少しだけ復習しつつ、ダウン症児のきょうだい児に特有とされる部分もご紹介します。
障害や病気を持つ子どもの兄弟であるきょうだい児は、他のお子さんと比べて、「親が自分に構ってくれない」と寂しさを感じる場面があります。
一方で、親御さん自身も障害のある子にどうしても時間が取られてしまうことへ罪悪感を抱いている場合もあると思います。
ただ、きょうだい児は幼い時でも、その親御さんの気遣いをしっかり感じ取っているという研究報告があります。
また、兄弟の障害や病気のことを年齢に応じて、精一杯理解し、協力しようという気持ちになることも多いようです。
兄弟姉妹の関係においては、ダウン症のお子さんのいる家庭の方が、お互いを温かく思いやる気持ちが強いという報告もあります。
もちろん、親御さんがダウン症のお子さんの方をより大切にしていると感じることもあるかもしれませんが、それがきょうだい児の心の成長を大きく妨げるわけではないようです。
ダウン症の弟をもつきょうだい児として育った私自身の経験も少しお話しさせていただくと、私はダウン症の弟がいることをマイナスに捉えたことはほとんどありません。
幼少期は入退院が多かったものの、幸い祖父母や叔母など親戚の手助けもあり、あまり寂しかった記憶はありません。
また、弟が原因で友人から嫌な思いをさせられたこともなく、むしろ弟は持ち前の明るさで私の友人たちにも愛されていたように思います。
その姉、という感じで、先生方にも気にかけていただいていたんだろうと振り返って思いました。
時には弟のせいにして、宿題を忘れてきたりと…いいように言い訳にして、したたかに生きていました。(笑)
きょうだい児の研究ではあまり言及されていませんが、障害のある子がいるからこそ、うまく切りぬけた場面があるきょうだい児もいるのではないでしょうか。
障害の有無に関わらず、そこはきょうだいとして、それなりに喧嘩もしながらお互いに成長してきたと思います。
一方で成人してから結婚などを考えた際に、夫側の親戚から障害の遺伝の有無について気にされてしまったりと、きょうだい児であることを実感する場面がありました。
私はダウン症が遺伝的に生まれる確率は極めて低いことをすんなり理解していただくことができましたが、そうはいかない場合も想像できます。
兄弟に障害があることで、思わぬ障壁に出会うこともありますが、それはきょうだい児だからではありません。
社会にある障害が人生の邪魔をしてくることは、きっときょうだい児だけではないと私は考えています。
社会に障害がある以上は辛い思いをすることもあるかもしれませんが、最近はその辛さへの理解やサポートも増えてきています。
次の章ではそのサポートをご紹介します。
きょうだい児へのサポート
以上のように、ダウン症児のきょうだい児は、他のきょうだい児同様の悩みを抱えつつ成長していきます。
どうしても寂しさや「いい子」でいなくては、という気負いが生まれやすいきょうだい児。
その認知度も近年上がってきています。
そんなきょうだい児へのサポートとしては、以下の3点が考えられています。
①他のきょうだい児と出会う機会を持ち、仲間を発見する
②いつも「いい子」でいるからこそ、甘えたり無理を親に聞いてもらえるような体験
③親自身がきょうだい児との1対1の時間をしっかり確保する
このように、きょうだい児同士での繋がりや、「親と自分だけの時間」を感じられるようにサポートしていくことが、心の支えとなりそうです。
最近では、「NPO法人しぶたね」(HP:NPO法人しぶたね)さんなど、きょうだい児サポートをメインに活動されている団体やコミュニティが増えてきています。
このような活動に親子で参加してみたり、意図的に親子の時間をつくっていくことが、きょうだい児の精神的なサポートに繋がるのではないでしょうか。
また、きょうだい児へのサポートだけでなく、親へのサポートも重要です。
その意味でも、きょうだい児をもつ親同士が繋がり、支え合うきっかけとして、様々なイベントや活動に参加してみるのはいかがでしょうか。
まとめ
ダウン症のあるお子さんのきょうだい児は、様々な経験を通して成長していきます。
その成長を温かく見守り、必要な時にはそっと支えていくことが、私たち周りの大人の大切な役割ではないでしょうか。
弊社では、専門職、スタッフへのご相談も随時承っておりますので、お気軽にお声掛けください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【参考文献】
- 藤井和枝,「ダウン症児のきょうだい支援 : 保護者の意識ときょうだい児の受けとめ方との違い」,2006, 浦和論叢 (21), 71-85
- 阿部美穂子ら他3名,「障害のある子どものきょうだい児を育てる親の悩みに関する質的検討ーアンケートの自由記述分析ー」,2022,山梨県立大学看護学部・看護学研究科研究ジャーナル⑻‐1,11‐2
前の記事へ
次の記事へ