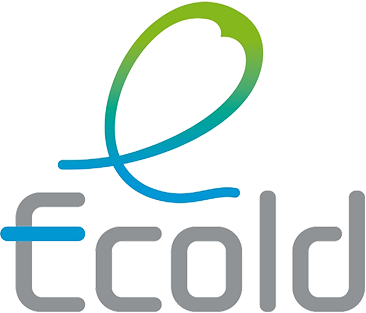エコルド川口教室代表野口×PECS導入実践者の上田さんの対談~後編~
こんにちは。ガイドヘルパーとして働いております、るりと申します。
ダウン症で重度知的障害を持つ弟がいる、姉でもあります。
こちらの記事は、PECS導入実践者の上田さんと弊社代表の野口との対談の後編です。
前編をまだお読みでない方は、ぜひ前編からご覧ください。
本記事では、以下の項目のうち、後半の「4.PECSの効果と実践方法」を取り扱います。
1. 対談者の紹介
2. 対談概要
3. PECS導入背景と課題
4. PECSの効果と実践方法
5. PECS導入に向けての環境整備
それでは後半もお二人の対談をお楽しみください。
*本記事では、障害を社会モデルで捉え、社会側にある障害に自覚的になり、改善するように働きかけたいという願いを込めて、あえて「障害」と表記します。
目次
4. PECSの効果と実践方法
(以下、敬称略)
上田: 何歳になってからもスタートできるんですね。
40歳の方のトレーニングをしてた事例を動画で見たこともあります。
表情がどんどん変わっていって、 要はおどおどしなくなってる。
野口:そうなんですね。
上田: はい。もう堂々と「これをしたい」って。反対に、「したくない」とか。
そうやってこう、人生の質っていうんですかね、生活の質が、コミュニケーション取れることで上がるんですよね。
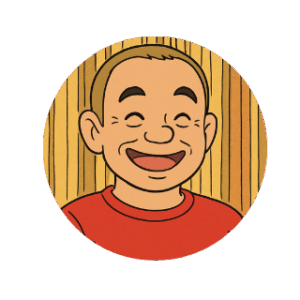 人生の質っていうんですかね、生活の質が、
人生の質っていうんですかね、生活の質が、
コミュニケーション取れることで上がるんですよね。
野口:どんどん伝えたくなる?
上田:そうなんです。最初は「ほしい」からスタートするんですけど。
後にはもちろん「いらない」もそうですし、自分が言うだけじゃなくて、「ちょっと待って」ってあるじゃないですか。
「ちょっと待ってね」っていう練習をするので、ちょっと待てるんです。
るり: 大事ですね。
上田: はい。待つ意味が分かってるので待てる。
今の行動障害と言われる人は、大体待つ意味が分からなくて、伝えられなくて、暴れたりして、怒られるじゃないですか。
でも本人は元々「ちょっと待って」って言いたかっただけの時もある。
そこがやっぱコミュニケーション取れることによって、強度行動障害と言われなくなくなる。暴れずに済むので。
野口: うん、そうですね。伝え方がわかんないからですよね。
上田: そうです。 PECSが唯一具体的に伝えられる技という風になっているので。
じゃあ、やっぱり支援者が知って、学んで、実践していったらいいなって進めているところです。
野口: PECSじゃなくても、色々伝わることってあるよねって思う職員もいて。
それも事実ではあると思うんですけども。
でも、やっぱり想像の域は出ないですよね。支援者の。
その子が本当に伝えたいことなのかどうかっていうのはわからなくて。
上田: 気持ちをどう伝えてもらって聞くか、どう想像するか。
誰が大切なのか っていうのは、保護者でもないし、支援者でもないし、本人の考え、思いをどうにか捉えるってなってくると、PECS大事やなって繋がるんです。
るり: 本人さんの意思をちゃんと汲み取れるために、PECSが大事だよねって認識してもらうと、法人の中でも、保護者さんにも理解が深まりそうですね。
5. PECS導入に向けての環境整備
るり:PECSを広める時に、(支援者同士が)相談し合える関係性というか、土壌作りみたいなところは、結構上田さんの中では大事って考えられてるんですよね。
上田: そうそう。
PECSという手段を使って、僕は関係性を作っていく、人材育成の1つにしました。
(障害を持つ子どもとのコミュニケーションの)成功体験積んでない職員もいっぱいいてるのし、やっても無駄とかっていう人もいてるので、そこの土壌作りをずっとやってる感じですね。
よく職員が、「ご飯食べる?」って言ったら『食べる』って言ってくれるから、コミュニケーションできてるっていう人もいるんです。
でもそれは「応答コミュニケーション」でしかないんで。
野口:ありますよね。訊いたら(そのままの)返事が返ってくる。
上田: これは質問されたことに答えているだけで、別のコミュニケーションになってる。 自発的なコミュニケーションを大切にしてるPECSっていうのがすごくいいなと思うんですよね。
るり:上田さんの事業所も、職員さんも最初何も知らないとこから始まっているんで。
PECSの意義みたいなところを理解してもらうところをきっかけに、もしかしたら職員さんのモチベーションにも繋がっていって、もっと こう、コミュニケーションしやすくなるっていうのは間違いないとは思いました。
上田:そうですね、そう思うなぁ。
野口: そうですね。質問いいですか?
PECSの道具あるじゃないですか、絵カードとファイルみたいな。
それって標準品買われてるんですか?それとも自作?
上田:自作です。買ったやつもありますけど、家族さんが買ったり。
野口:家族さんが?
上田:必要やと思ってる人はもう買って来はります。
野口:では、自作なり買うなりをやっぱり保護者さんの方に求めるんですか?
上田:うち(事業所)では簡易的なものを作ったりとかしてます。
家族さんからスタートっていうのはなかなか難しくて、やっぱり家族さんも忙しいので、やり方わからんとか。
そこで、一緒に考えはしますけど、うちで準備するのは、もう手作りのやつで作ってますね。
あと今はipadで使ってやってる子もいてますけど。
でもそれの前に、ちゃんとそのアナログのやつでや力つけてやっとかんと、(iPadの)電池なくなった時とか、防災の時とかの時に困るから。
スタートはアナログの絵カードからです。
るり:それはお家に帰るときにも持たせるんですか。事業所で作ったやつを?
上田:うちのやつは持って帰らないです。
るり: じゃあ、お家では保護者さんの中で興味ある方が、ご準備をご自分でされるって
感じですかね?
ご家庭でも継続したい場合は。
上田:そうですね。そこはちょっと家庭との連携になってきます。
野口:じゃあ、そのPECSの道具は事業所の中に何人か分、もう常に準備されてて、コミュニケーション取りたい子供がそれを取ってやると。
上田:そうそう、そういう形です。
家族さんがもう持ってきて、それ(ご家庭で使っているPECSの道具)を使って、事業所でも支援に使っていることもあります。
野口: 親御さんの方に自作するなり 買うなりしてもらって。
常に子供はそれを持ち歩いていて、どこに行くにもですね。
という形が理想(同じツールを利用し続ける方が効果的)なんですね。
上田: そうですね。それと同時に、PECSを使う意味も理解してもらえるといいかなと思います。
るり: ご家庭を中心に、PECSを使って24時間コミュニケーションをしていく環境を整え
られると、お子さんのコミュニケーション発達により効果的なんですね。
…お時間になりますので、本日はこのくらいになってしまいますが、大丈夫ですか?
野口:お忙しいところありがとうございました。大変参考になりました。
上田: こちらこそ、野口さんのところでも使ってもらえたら嬉しいです。
ありがとうございました。
まとめ
お二人の対談は小一時間ほど続き、PECS導入に向けて貴重なお話を伺うことができました。
本記事で扱えた内容はその一部になりましたが、PECS導入の意義が少しでも伝われば非常にうれしく思います。
お子様のコミュニケーション支援ツールとしてPECSを導入する場合は、できるだけ同じツールを、どんな場所でもどんな人とも使い続けることが効果的です。
そのために、ご家庭と事業所の連携が不可欠となってきます。
弊社でPECSを導入する前に、ご家庭での導入をご検討いただいている場合も、スタッフにご相談いただき、ツールをご持参いただくことは可能です。
お子様とのコミュニケーションの一助になれるように、精進してまいります。
PECS以外でも、支援方法についてのご相談は、ご利用の際にお気軽にお申しつけください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
次の記事へ